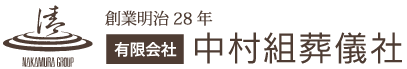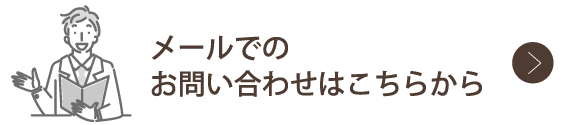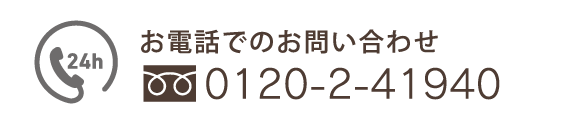- HOME
- > いまさらですが、「家族葬」って何?①
いまさらですが、「家族葬」って何?①
2025.03.05

この老舗の知恵袋も回数を重ねてきましたが、触れていそうであまり深く触れていなかった「家族葬」を考えます。
いまさらですか? いいえ、家族葬が広がったいまだからこそです。
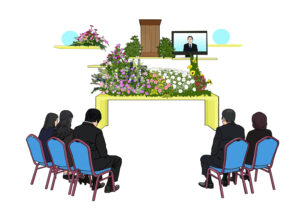
お葬式は規模や参列者の数で価値が決まるわけではありません。「思いやり溢れるお葬式」を考えていきましょう。
家族葬にきちんとした定義はない
実は「家族葬」という言葉にきちんとした定義はありません。
そもそも葬祭業は許認可制ではなく、国の公的機関としての監督官庁はありませんので国からきちんとした指針が出たり、行政的指導があるわけではありません。
(なので、品位に欠ける葬儀会社もいるようです。)
あるのは公正取引委員会による暫定的定義です。
「親族や親しいご友人など親しい関係者のみが出席して執り行う葬儀」
「参列者50名未満の葬儀を家族葬として定義する」
葬儀会社各社がHPなどで謳っている家族葬は、各社が考える家族葬のあり方であって、一律に定義されたものではありません。
なので、よく読んでみると、微妙にニュアンスが違います。

最近はこの様な格式ある白木の祭壇を見かけることも減ってきました。もちろん弊社はこれです。
家族葬の歴史
家族葬という言葉が出てきたのが20年くらい前ではないかと思います。
それ以前は「家族葬」という言葉はなく、「社葬」「一般葬」「密葬」というものがお葬式の形を表す言葉でした。
(それぞれがどの様な葬儀を指すのかは今回割愛します。)
「家族葬」登場の前の段階は、自宅葬から斎場でお葬式を行う様になり、大きな祭壇に大勢の参列者、しめやかながら派手な演出に、高い費用が当然の様な風潮でした。
もちろん世の流れ、世のニーズもあってのことですから、これが今にして思えば・・・云々ということはありません。
(家族葬も世の流れ、世のニーズがあってこそのものです。)
この後現在に至るまでの「葬儀代は高い」という拭いきれない一般的なイメージはこの時代に生まれたものでしょう。
しかしその後、この大規模なお葬式が費用の面など様々な面から少しずつ改めれらていき、その流れを掴んだどこかの葬儀会社が「家族葬」を謳って小規模なお葬式を提案したのが始まりの様です。
それからマスコミに取り上げられるなどじわじわと浸透し始めて、いまやお葬式のほとんどが「家族葬」といっても差し支えないがないでしょう。正に時代にマッチしたということでしょう。
恵方巻と家族葬は似たもの同士?
同列には語るのは違うかもしれませんが、恵方巻に似たものを感じます。
ここ北九州・小倉には恵方巻などの風習はありませんでした。
全く馴染みのないこの恵方巻が全国的になったのはここ20年くらいの話です。
昭和世代からいわせると、突然やってきてお店に大量に陳列され始めたよくわからない風習です。
諸説ありますが、実は江戸時代から大阪の一部地域にあった風習らしく、それが、広島県の某コンビニの一部の店舗で売り出され、その後その某コンビニの戦略でやや無理やり一般的になったと流れの様です。
家族葬も似た様なもので、ある葬儀社から始まったものが戦略的に「家族葬」という言葉を使うようになり時代背景とマッチして日本全国に広がっていったという感じなのだと思います。
今回はここまで。次回は家族葬の真実に迫ります。