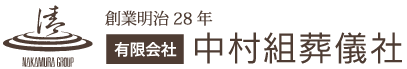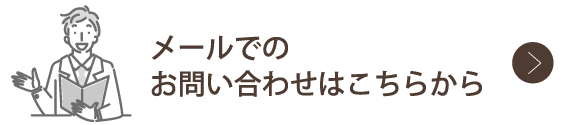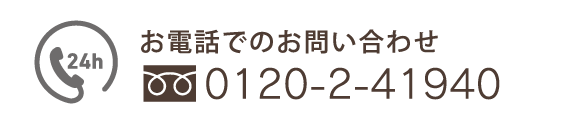- HOME
- > お葬式の費用について-(ほぼ)必ず必要な費用①-
お葬式の費用について-(ほぼ)必ず必要な費用①-
2025.11.10

今回からしばらくはお葬式にかかる費用の細かいところを見ていきます。
今回はお葬式にほぼ必ずかかる費用について触れていきます。
【お迎え搬送車(寝台車)】
病院や施設などの亡くなった場所から葬儀場(斎場)に故人をお連れするための搬送用車両。
自宅で亡くなりそのまま自宅葬にする場合や亡くなった場所等安置されている場所から出棺し、直接火葬場へ行く場合は不要。
また病院等で亡くなり、一度自宅等へ連れて帰り、後日葬儀場にお連れする場合、霊柩車(搬送)は2回の運行となり費用が増えます。
各社のプランの場合には搬送車の2回目の運行が別料金となることが多い様です。
また搬送車両の使用料は走行距離で決まってくることが多いので、例えば北九州市小倉南区でお葬式をするのに、亡くなった場所が小倉南区内なのか福岡市内なのかでは搬送料は随分金額が違ってきます。
ほとんどの場合、この搬送料は走行した距離で決まり、個別に料金が設定されていますが、プランがある場合にはプランに含まれることが多い様です。
いろいろな葬儀会社のHP等を見る感じでは、プラン内に収まる距離は長くても30km以内くらいで、10km以内というところも結構あります。
つまりこの場合、搬送距離が10kmを超えると追加料金がかかることになります。
【霊柩車(出棺)】
葬儀場やその他お葬式を行った場所から火葬場へ向けて柩を載せる霊柩車(出棺)。
火葬場へは柩の状態で入る必要があり、柩を載せて走ることが出来る霊柩車は必ず必要となります。
運行の考え方は各葬儀会社で異なるので何ともいえませんが、北九州市の葬儀会社の葬儀場から北九州市内の火葬場にお連れするのであれば、基本料金の範囲、もしくはプラン内の範囲とするところが多いのではないでしょうか。
また霊柩車の車種も複数あるので、それぞれ金額が異なるでしょう。
先ほども少し触れましたが、搬送・出棺のいずれについても霊柩車の運行について、各葬儀会社にそれぞれ考え方や料金の基準があります。
同じ距離だからどの葬儀会社も料金が同じということには必ずしもなりません。
また一見変な話ですが、葬儀会社によっては、プランの中に搬送・出棺の霊柩車のどちらか一方の料金しか含まれておらず(もしくは両方含まれていない)、当たり前の様に追加料金がかかる場合もある様です。
おそらく理由としては、搬送であれば「距離が一定でない」とかで、出棺であれば「車種が多いから」とかでしょう。
霊柩車の費用以外でも言えることですが、「お葬式なんだからあって当たり前」が当たり前だとは限りません。

葬儀会社のHPにこういうアイコンがよく使われます。わからないものがあればどんどん尋ねることが大事です。
【棺】
亡くなった方のお身体を納める容器。棺桶。
日本の火葬場においては柩に納めた状態でないと受け付けてもらえませんので、必ず必要となります。
木材を合わせたベーシックで極々シンプルなものから、いくつもの彫刻を施したものや装飾の入った布で覆われているものなどがあります。
棺は「高額請求トラブル」のタネになるもののひとつです。
木棺、桐平棺等と呼ばれるベーシックな棺と手の込んだ装飾がついた棺では金額が変わってきます。
また一般の方でも「どうせ燃やすものだから」と考える人もいれば、「最後だから装飾のついた立派な棺がいい」と考える人もいます。
故人の生前の生き方や想いを感じられるもの、残されたご家族や亡くなった本人の意向が反映されれば、それが一番なので、どのような棺を使っていただいても問題はないのですが、葬儀会社の担当者は高いものを勧めてくることも多いのも事実です。
それ自体が悪いことではないのですが、「こんな簡素で粗末な棺では故人様がかわいそうです。」(だったら葬儀社がそんな粗末なものを使うなって話ですが)みたいな言い方で、悲しい想いをしているご家族につけこんで高価なものをゴリ押しする残念な事例があるのもまた事実。
(因みに弊社ではこの様なことはありません。)
ご家族が納得しないまま高い棺をゴリ押しすると、当然それは「高いものを売りつけられた!」となってしまいます。
棺の形状・材質・歴史など棺について深掘りしたいところですが、それを語っているととてつもなく長くなってしまうので、今回は割愛します。
(弊社HPの「中村組葬儀社の話」の中に棺の歴史に触れる箇所があります。ぜひご一読を。)
なお、「ひつぎ」には「棺」という字と「柩」という字があります。「棺」は中が空っぽの状態のもの、「柩」はご遺体が納められたもの、という使い分け方が一般的です。だから火葬場に向かう車は霊「柩」車なのです。
今回はここまで。
次回もお葬式の費用について、(ほぼ)必ず必要な費用を見ていきます。