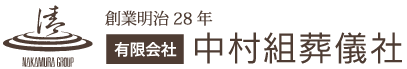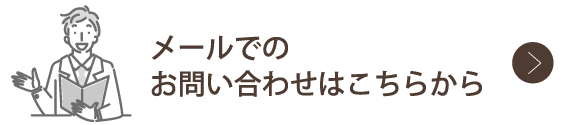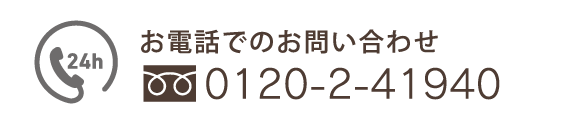- HOME
- > 一日葬を考える①
一日葬を考える①
2025.09.28

今回は最近葬儀関連の広告やニュース等で目にすることが多くなった「一日葬」について深堀りしてみます。
前回の最後にお話した通り一日葬とは
読んで字の如く、「一日で行う葬儀」を指します。
多くの場合、仏式の葬儀では通夜・葬儀と二日に亘って(場合によってはさらに延びることもありますが)行われますが、このうち通夜を省略して葬儀(及び告別式・火葬)を一日で執り行う葬儀という解釈が一般的だと思います。
通夜の葬儀化の現状
元々、通夜は夜伽(よとぎ)と呼ばれて、身内の方が亡くなった方を生きていた方として一晩中夜を通してお世話していたことがルーツだそうです。(諸説あります)
僧侶の方は、その対象の人物に対し、通夜は生きていた方の最後の夜として接し、葬儀は亡くなった方として接し、その亡くなった方を弔う儀式ということになります。
近年では、「通夜の葬儀化」的な雰囲気があり、人によっては「葬儀が二回ある」という風に感じていらっしゃる方もいるのではないかと思います。
ですが、通夜が元々どの様なルーツであったかということを考えるとその違いを感じることが出来るのではないでしょうか。
一般の方はあまり難しいことはあまり考えず、「通夜は故人との最後の夜、葬儀は故人を弔う最後のお別れの場」という認識でいいのではないかと思いますが、実は別物という認識も必要かとは思います。

ごくごく普通の一般の方の家族葬のイメージはこんな感じでしょうか。皆さんの家族葬のイメージを教えてください。
一日葬のデメリット
一日葬は近年の新しいお葬式のスタイルです。
お寺様的には通夜と葬儀は別物という考え方であること考慮すると、「通夜を省く」という意味が大きい一日葬について、難色を示すお寺があっても不思議ではありません。
これが一日葬のデメリットというか壁のひとつで、葬儀を依頼する菩提寺側が、通夜を省く一日葬を想定していなかったり、認めない・お許しが出ないなどということもあり得ます。
(もちろんこれはこれで尤もな理由です。)
その他、新しいスタイルゆえ、通夜を省き葬儀のみを行うことについて「通夜・葬儀」をワンセットと考える親族や故人の関係者の理解を得られず反対されることも十分考えられます。
特に親族の中に発言力が強い方がいる場合は特に慎重にことを進める必要があります。
また儀式を一日に限定してしまうことで、参列出来ない方が多数出ることも考えられます。
しかし実はよくよく考えると、一日葬を選択し通夜を省いても、お葬式全体、つまりご逝去から火葬までの日程が短縮されるとは限らないのです。
人は亡くなっても特別な事情がない限り原則、死亡時刻から24時間経過しないと火葬が出来ません。
直葬の話でも触れましたが、よほどの条件が整っていなければ直葬が出来ないのと同様に、一日葬を選択したからイコール火葬までのスケジュールが短縮されるという訳ではありません。
つまり「通夜の日程にあたる日」はほとんどの場合存在します。
一日葬のデメリットは親族や関係する人々の理解が得られにくいことや菩提寺が難色を示す可能性が高いことが大部分を占めるという感じになるでしょう。
今回はここまで、次回も一日葬についての続きです。