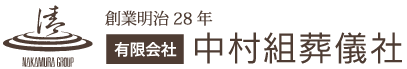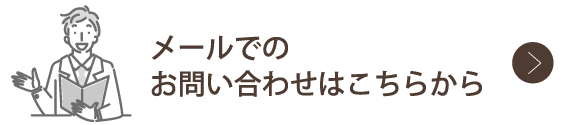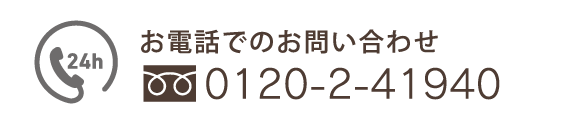- HOME
- > 小倉北区熊本・大畠・宇佐町地区の昔話
小倉北区熊本・大畠・宇佐町地区の昔話
2025.08.23

この老舗の知恵袋では基本的にお葬式に関するお話をメインに綴っていますが、たまには全く関係ないことをお題にしてみようと思います。
弊社中村組葬儀社には本社・城野斎場とは別にもうひとつ、小倉北区熊本に式典会館という斎場があります。
弊社の創業の地は小倉北区紺屋町ですが、平成6年(1994年)に本社を移転し、本社機能を持つ城野斎場ができました。
それから遡ること14年、昭和55年に式典会館ができました。45年前の話です。
当時はまだ、お葬式を自宅やお寺で行うことが当たり前だった時代に、式典会館が作られました。
とここまで紹介をしておきながら、式典会館の話は置いといて(笑)、ここからは式典会館のある熊本地区やその周辺の昔の話です。

リブホール大畠店裏手(奥)から熊本方面(手前)へ向かう道路。右手の住宅地の基礎部分が高くなっているのは鉄道の築堤の名残と思われます。
小倉炭鉱
福岡県の炭鉱といえば、田川・飯塚・嘉麻(山田)・直方などの広い範囲にわたる筑豊地方や大牟田地域が有名ですが、ここ小倉にも炭鉱がありました。
古谷鉱業という会社が操業を始めたその名も小倉炭鉱は、弊社の小倉北区熊本の式典会館にほど近い大畠・宇佐町にありました。
具体的な場所については「小倉炭鉱発掘記」などの資料によると、現在のリブホール大畠店の裏手辺り(大畠1丁目)とローソン小倉宇佐町店裏手辺り(宇佐町2丁目)にあったようです。
坑道は足立山西麓から砂津・関門海峡に向かって伸びていたとのこと。
昭和13年(1938年)に操業を開始し、昭和40年(1965年)には閉山したので、操業期間はわずか27年。
坑道の落盤事故や湧水・水没事故の影響で操業を停止されたといわれ、広寿山福聚寺にはその事故の犠牲者を追悼する「小倉炭鉱殉職者慰霊塔」があります。
実は小倉炭鉱の歴史を紐解くとさらに古く、足立山西麓に明治20年開坑した足立炭坑からスタートします。
これ以降、足立一帯を掘り始めては閉山を繰り返し、また経営者や名称も市況の好不況を受けてコロコロ変わるような状況だったようです。
炭坑の名称変更は以下の様になるようです。
・足立炭鉱→第二鷲峰炭坑→鷲峰炭坑→大畠炭坑
・熊本炭坑→(第一)鷲峰炭坑→第二鷲峰炭坑→新鷲峰炭坑
・第三鷲峰炭坑
・大畑炭坑→足原炭坑→清磨炭坑→吉熊炭坑→足原炭坑→足立炭坑→共栄炭坑
それ以外にも、第一神代炭坑、撰炭坑、勝山炭坑、富野炭坑などがあったという記録も残っていて、それらの中の一つを受け継ぐ形で後の小倉炭坑があったと考えられているようです。
小倉炭鉱時代の昭和23年頃には菊が丘住宅・藤が丘住宅等の社宅や炭坑附属病院などが周囲にあったとのことですので、炭坑の規模もある程度のものがあったと想像できます。
(もしかすると、住所の名称としては残っていないけれども、これらの炭坑の名称の一部が地域の古い呼び名や通称・俗称などで、残っているかもしれません。この地域に長く住まれている高齢の方なら何かご存じかもしれませんね。)

現在の妙見駅跡付近(中央の白い四角が「中津街道の跡」の説明看板)

当時の妙見駅の様子(上の画像と同じ位置かは不明)
また大畠と宇佐町の炭坑の間をすり抜けるような形で鉄道も敷設されており(小倉鉄道)、足原公園の池の裏手(小倉北区役所によって設置された「中津街道の跡」の説明看板がある付近一帯)には広い構内を有し、貨物の取り扱いもある妙見駅がありました。
また、現在北九州市民球場やメディアドームがある辺りは以前は湿地帯で、石炭を掘った際に出たボタ(くず石炭などの排出物)は、そこの埋め立てに使ったという話もあります。(なので小倉には筑豊の様なボタ山がないとのことらしいです)
今回はここまで。次回は今回の続きのお話です。